採用コラム採用のやり方が分からない初心者必見!手法選びから面接まで成功する採用活動の進め方
最終更新日:2025年11月21日
「採用活動を任されたけれど、何から始めればいいか分からない」
「どの採用手法を選べば効果的なのか知りたい」
そんな悩みを抱えていませんか?
本記事では、採用のやり方を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
15の主要な採用手法の比較から、採用計画の立て方、面接の進め方まで、成功する採用活動に必要な知識とノウハウをすべてお伝えします。
この記事を読めば、自信を持って採用活動をスタートできるでしょう。
採用活動を成功させるためには、まず全体の流れを把握することが重要です。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る
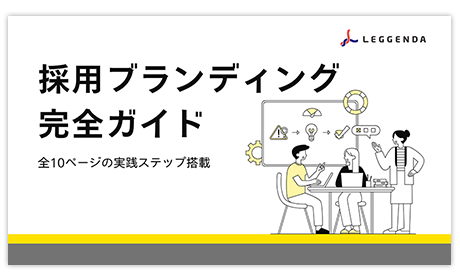 資料を受け取る
資料を受け取る
まずはここから!採用活動の全体像と流れ
採用活動を成功させるためには、まず全体の流れを把握することが重要です。
やみくもに施策を打つのではなく、各ステップの目的と役割を理解することで、一貫性のある戦略的な採用活動が可能になります。
- ステップ1:採用計画の立案
- ステップ2:募集開始
- ステップ3:書類選考
- ステップ4:面接実施
- ステップ5:内定通知
- ステップ6:内定者フォロー
- ステップ7:入社後サポート
特に最初の「採用計画」は、以降のすべてのステップの土台となるため極めて重要です。
例えば、採用計画で求める人物像が曖昧だと、その後の募集や選考で判断基準がブレてしまい、結果的にミスマッチが生じる可能性が高まります。
まずはこの全体像を掴み、計画的な採用活動の第一歩を踏み出しましょう。
【目的別】主要な採用手法15選のメリット・デメリット・費用
現代の採用活動では、従来の求人広告だけでなく、多様な手法を戦略的に組み合わせることが成功の鍵となります。自社の採用課題や予算、求める人材像に応じて最適な手法を選択しなければ、コストと時間だけがかかり、成果に繋がらないという事態に陥りかねません。
そこで本章では、主要な採用手法15選を以下の4つのカテゴリに分類し、それぞれのメリット・デメリット、費用感を詳しく解説します。
-
能動的アプローチ(攻めの採用):企業側から積極的に候補者にアプローチする手法群
-
受動的アプローチ(待ちの採用):求職者からの応募を待つ従来型の手法群
-
関係構築型アプローチ:長期的な関係性を築きながら採用に繋げる手法群
-
専門サービス活用型:採用のプロフェッショナルや専門プラットフォームを活用する手法群能動的アプローチ(攻めの採用)
これらの特徴を理解することで、自社に合った採用戦略を立てるための具体的なヒントが得られるでしょう。
まずは、企業側から積極的に動く「能動的アプローチ」から見ていきます。
これは、いわゆる「待ち」の姿勢ではなく、自ら優秀な人材にアプローチしていくスタイルです。転職を積極的に考えていない層にもリーチできるのが魅力です。
ダイレクトリクルーティング:欲しい人材にピンポイントでアプローチ
ダイレクトリクルーティングは、企業が「欲しい」と考える人材へ、直接アプローチできる攻めの採用手法です。
LinkedInやWantedlyといったプラットフォームを活用し、企業の採用担当者が候補者へ直接スカウトを送るのが一般的な進め方です。
-
メリット: 採用の質を格段に高められるのが最大の強みです。その理由は、求人広告では出会えない、転職を具体的に考えていない優秀な層にも直接アプローチできるからです。特定の開発経験を持つエンジニアを探す際に、候補者の公開プロフィールを見てから「あなたの〇〇のご経験は、弊社の新プロジェクトに不可欠です」と個別にスカウトを送ることで、ミスマッチを防ぎつつ質の高い候補者と接点を持つことができます。
-
デメリット: 候補者の選定からメッセージ作成、フォローアップまで、採用担当者の工数が大幅に増加する点が挙げられます。また、プラットフォームの利用料として月額50万円程度がかかる場合もあります。
-
こんな企業におすすめ: 特にITエンジニアや専門職など、高度なスキルを持つ人材をピンポイントで探している企業に最適です。
ヘッドハンティング:トップクラスの人材をスカウト
ヘッドハンティングは、企業の経営層や特定分野で極めて高い専門性を持つ人材など、トップクラスの人材を獲得するための採用手法です。採用のプロが企業に代わり、候補者を探し出して引き抜きます。
-
メリット: 最大のメリットは、通常の採用市場には現れない、極めて市場価値の高い人材を獲得できる可能性が生まれる点です。というのも、競合他社で活躍中のキーパーソンなど、転職を考えていない層にも直接アプローチできるからです。
例えば、新規事業の責任者を探す際に、業界内で実績のある人物をリストアップし、ヘッドハンターを通じて非公開で接触を図るといった活用が可能です。企業の重要ポジションを極秘で採用したい場合に特に有効です。
-
デメリット: 一般的に、採用決定時に年収の50%以上という高額な成功報酬が発生します。また、候補者との信頼関係構築に時間がかかるため、即効性を求める場合には不向きかもしれません。
-
こんな企業におすすめ: 経営幹部や事業の根幹を担うキーパーソンなど、企業の未来を左右する重要な人材を採用したい場合に検討すべき手法です。
リファラル採用:社員のネットワークを活かす
リファラル採用は、自社の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法です。「社員紹介制度」とも呼ばれ、企業文化にマッチした人材が集まりやすいのが特徴です。
-
メリット: 採用コストを大幅に抑えつつ、入社後の定着率向上が期待できます。その背景には、紹介者である社員が企業の文化や働き方を深く理解しているため、候補者とのミスマッチが起こりにくいという点があります。
実際に、紹介インセンティブ(1人あたり5万円~20万円程度)を設定し、社員に制度を周知することで、人材紹介会社に支払う手数料(年収の30~35%)と比較して大幅なコスト削減が可能です。
-
デメリット: 社員個人の人脈に依存するため、紹介される人材の数や職種に偏りが出やすい点が挙げられます。制度を形骸化させないためには、社員への丁寧な説明と継続的な啓発活動が不可欠です。
-
こんな企業におすすめ: 採用コストを抑えつつ、自社の文化に合う人材を確実に見つけたい企業や、社員のエンゲージメントが高い企業に特に有効です。
待ちの採用:応募を待つ王道スタイル「受動的アプローチ」
次に、求職者からの応募を待つ、従来型の「受動的アプローチ」を見ていきましょう。多くの人にリーチできるのが魅力ですが、他社との差別化が鍵となります。
求人広告(求人サイト・求人情報誌):広くリーチするならまずこれ!
求人広告は、リクナビNEXTやマイナビ転職といった求人サイトや情報誌に情報を掲載し、広く応募者を募る最もポピュラーな採用手法です。
-
メリット: 多くの求職者に一度に情報を届けられるため、母集団形成に非常に効果的です。というのも、転職を考えている多くの人がこれらの媒体を利用して職種や勤務地で検索するため、条件に合う候補者からの応募が期待できるからです。
特に、全国の営業職を5名募集するといった大量採用のケースでは、幅広い層にアプローチできる求人広告が非常に有効な手段となります。
-
デメリット: 4週間で20万円~50万円程度の掲載費用がかかります。また、多くの企業が同じ媒体に掲載するため、自社の求人が埋もれてしまう可能性があり、候補者の目を引く求人票作成の工夫が求められます。
-
こんな企業におすすめ: 幅広い人材層にアプローチしたい企業、特に採用の母集団形成を重視する企業に適しています。
ハローワーク:無料で求人を掲載できる安心感
ハローワークは、国が運営する公共職業安定所であり、無料で求人を掲載できるのが最大の魅力です。
-
メリット: 採用コストを一切かけずに募集活動ができる点が、他の手法にはない大きなメリットです。なぜなら、国の公的機関であるため、企業は無料で求人情報を登録でき、助成金の対象となる場合もあるからです。
例えば、採用予算が限られている中小企業が、最初の採用活動としてハローワークに登録するケースが多く見られます。特に地域に根差した人材を採用したい場合に強みを発揮します。
-
デメリット: 求人票に記載できる情報量が限られており、企業の魅力を十分に伝えきれない場合があります。また、応募者のスキルや経験にばらつきが見られるため、書類選考での見極めがより重要になります。
-
こんな企業におすすめ: 採用予算が限られている企業や、地域に密着した採用を行いたい企業に最適な手法です。
自社採用サイト(オウンドメディアリクルーティング):企業の魅力を発信する基地
自社採用サイトは、企業の理念や文化、働く人の様子などを自由に発信できる、自社専用の採用プラットフォームです。
-
メリット: 求人媒体のフォーマットに縛られず、企業の魅力を深く、かつ多角的に伝えられる点が強みです。なぜなら、動画や社員インタビューといった多彩なコンテンツを通じて、候補者の共感を呼び、入社意欲を高めることができるからです。
例えば、「社員の一日」といったコンテンツで具体的な働き方を提示したり、開発チームのブログで技術的な挑戦を発信したりすることで、求職者は働くイメージを具体的に持つことができます。これは、長期的な採用ブランディングの資産となります。
-
デメリット: サイト制作には50万円~200万円程度の初期費用がかかる場合があります。また、サイトへの集客にはSEO対策や広告出稿といった別途マーケティング施策が必要となり、効果が出るまでに時間がかかることもあります。
-
こんな企業におすすめ: 企業の独自性や文化を強くアピールしたい企業や、長期的な視点で採用ブランディングを強化したい企業に有効です。
関係構築型アプローチ:長期的な視点でファンを作る
そして、即効性よりも、長期的な関係構築を重視するアプローチです。企業のファンを増やし、質の高いマッチングを目指します。
SNS採用(ソーシャルリクルーティング):日常からファンを育む
SNS採用は、X(旧Twitter)やFacebookなどを活用し、企業の日常や働く人のリアルな姿を発信することで、候補者との自然な接点を作る採用手法です。
-
メリット: 最大のメリットは、企業の「ファン」を育成し、応募への心理的なハードルを下げられる点です。なぜなら、候補者は日々の投稿を通じて企業の雰囲気や価値観に触れることで、親近感を抱き、自然な形で応募を検討するようになるからです。
例えば、社内イベントの様子や、社員がランチを楽しむ風景などを投稿することで、求人票だけでは伝わらない「リアルな職場」を伝えることができます。特に若手層やクリエイティブ職の採用に効果的です。
-
デメリット: 運用コストは比較的低いものの、継続的な投稿と魅力的なコンテンツ作成には専門的なスキルと労力が必要です。また、意図しない形で炎上するリスクもあるため、投稿内容には細心の注意が求められます。
-
こんな企業におすすめ: 若手層やクリエイティブ職の採用を強化したい企業、また企業文化を発信してファンを増やしたい企業にぴったりです。
ミートアップイベント:カジュアルな交流から生まれる縁
選考とは別に、特定のテーマで社員と求職者がカジュアルに交流する場を設ける採用手法です。
-
メリット: 候補者との自然な関係構築を通じて、入社後のミスマッチを減らせるのが大きな利点です。なぜなら、候補者は現場社員との直接的な対話を通じて、企業の雰囲気を肌で感じ、自身の価値観と合うかを判断できるからです。
例えば、「最新技術に関する勉強会」や「業界の未来を語るセミナー」といった形式で開催し、イベント後の懇親会で社員と候補者がリラックスして話せる機会を作ることで、応募へのハードルを下げることができます。
-
デメリット: イベントの企画・運営には相応の工数が必要です。また、一度の開催で直接的な採用に繋がるケースは稀であり、継続的な開催によって効果が現れる長期的な取り組みとなります。
-
こんな企業におすすめ: 現場の社員と候補者の交流を重視したい企業や、採用候補者とのエンゲージメントを高めたい企業に適しています。
インターンシップ:未来の仲間と出会う場
インターンシップは、学生や求職者に一定期間の就業体験を提供し、企業と候補者の相互理解を深める制度です。
-
メリット: 入社後のミスマッチを大幅に減らせる点が最大のメリットです。なぜなら、実際の業務を通じて、企業は候補者のスキルやポテンシャルをじっくり見極めることができるからです。また、企業側も候補者の適性を判断しやすくなり、新卒採用においては、早期に優秀な学生との接点を持つことが可能になります。
例えば、新卒採用において、夏休みに2週間の開発インターンシップを実施し、優秀な学生には早期選考の案内を出すといった形で、未来のスター候補を早期に発掘することが可能です。
-
デメリット: 参加者の受け入れ体制の整備や、指導を担当する社員の確保など、一定のコストと工数が必要です。
-
こんな企業におすすめ: 新卒採用を強化したい企業や、候補者のポテンシャルをじっくり見極めたい企業に特に有効です。
専門サービス活用型:プロの力を借りて効率化
最後に、採用のプロフェッショナルや専門プラットフォームを活用する「専門サービス活用型」です。専門性とネットワークを駆使して、効率的な採用を実現します。
人材紹介(エージェント):採用のプロに任せる安心感
人材紹介は、採用のプロであるエージェントに、候補者探しから紹介までを委託できる信頼性の高い採用手法です。成功報酬型が一般的で、採用が決定した際に年収の30~35%を支払うことで、質の高いマッチングを実現します。
-
メリット: 採用活動の工数を大幅に削減しつつ、質の高い候補者と出会える点が最大のメリットです。なぜなら、採用のプロが企業の代わりに候補者の初期選考を行うため、自社の要件にマッチした人材だけが紹介されるからです。
例えば、採用が難しい管理職や専門職のポジションにおいて、転職市場には現れない優秀な人材をエージェントの非公開ネットワークから紹介してもらえる可能性があります。
-
デメリット: 費用が高額になるため、採用予算との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。
-
こんな企業におすすめ: 採用活動に十分なリソースを割けない企業や、即戦力となる経験豊富な人材を確実に採用したい企業に最適です。
参考記事:【最新版】エージェントコントロール完全攻略ガイド|“注力企業”になるための即実践ロードマップ
合同企業説明会・転職フェア:一度に多くの出会いを創出
合同企業説明会や転職フェアは、一つの会場に多数の企業と求職者が集まり、直接対話できるイベント形式の採用手法です。
-
メリット: 一度に多くの求職者と直接接点を持てるため、企業の認知度向上と母集団形成に効果的です。なぜなら、企業の知名度がそれほど高くなくても、ブースでのプレゼンテーションや個別面談を通じて、自社の魅力をダイレクトに伝えることができるからです。
例えば、IT業界に特化した転職フェアに出展すれば、すでに関連分野に関心を持つ候補者と効率的に出会うことができます。
-
デメリット: 10万円~50万円程度の参加費用がかかります。また、参加者の多くはまだ情報収集の段階であるため、イベント後の丁寧なフォローアップが採用成果を大きく左右します。
-
こんな企業におすすめ: 企業の認知度向上を図りたい企業や、多くの候補者と一度に接点を持ちたい企業に適しています。
大学・学校との連携:未来のスター候補を発掘
大学・学校との連携は、キャリアセンターへの求人提出や学内説明会の開催などを通じて、学生に直接アプローチする新卒採用向けの手法です。
-
メリット: 特定の専門知識を持つ学生や、自社が求める資質を持つ学生層にターゲットを絞ってアプローチできる点が強みです。なぜなら、大学の研究室やゼミと連携することで、教員から推薦を得たり、OB/OG訪問を通じて学生と個別の関係性を築いたりできるからです。
例えば、機械工学系の学生を採用したい場合、工学系のトップ大学と継続的な関係を構築することで、毎年安定して優秀な学生からの応募が期待できます。
-
デメリット: 採用対象が特定の学校に偏るリスクがあります。企業の多様性を重視する場合は、複数の異なる特色を持つ学校との連携を検討する必要があります。
-
こんな企業におすすめ: 新卒採用を強化したい企業や、将来性のある専門分野の若手人材を発掘したい企業に有効です。
その他の採用手法:多様なニーズに応える選択肢
ここでは、上記で紹介した主要な手法以外にも、特定のニーズに応える採用手法をいくつかご紹介します。
人材派遣:必要な時に必要な人材を
人材派遣は、必要な期間だけ、派遣会社から専門スキルを持つ人材を確保する柔軟な働き方です。
-
特徴: この手法のポイントは、繁閑の差が激しい業務や急な欠員補充に迅速に対応できる点です。なぜなら、企業が直接雇用するわけではないため、採用や労務管理のコストを抑えつつ、必要なスキルを即座に確保できるからです。
例えば、決算期の3ヶ月間だけ経理経験者を派遣してもらう、といった活用が可能です。時給制が一般的で、相場は2,000円~4,000円程度です。
-
ポイント: 長期的な人材育成には向きませんが、特定のスキルを持つ人材を短期間で確保したい場合に非常に有効です。
クラウドソーシング:スポット業務委託で専門スキルを活用
クラウドソーシングは、インターネットを通じて不特定多数の個人(フリーランスなど)に業務を委託する形態です。
-
特徴: この手法は、正社員を雇用せずに専門スキルを必要な分だけ活用できる点が特徴です。なぜなら、ライティングやデザイン、プログラミングといった専門業務をプロジェクト単位で発注できるため、固定費をかけずに業務を遂行できるからです。
例えば、Webサイトリニューアルの際に、フリーランスのデザイナーにロゴデザインだけを依頼するといった使い方が考えられます。
-
ポイント: 継続的な雇用関係は生まれませんが、優秀なフリーランスとの関係構築が、将来的な正社員採用に繋がる可能性も秘めています。
アルムナイ採用(カムバック採用):元社員の経験と信頼を活かす
アルムナイ採用とは、一度退職した元社員を再雇用する手法です。
-
メリット: 最大のメリットは、即戦力としての活躍が期待できる点です。なぜなら、元社員はすでに企業文化や業務内容を深く理解しているため、オンボーディング(入社後の教育)にかかる時間やコストを大幅に削減できるからです。
例えば、他社で新たなスキルやマネジメント経験を積んだ元社員に、以前より高いポジションで復帰してもらうことで、組織の活性化にも繋がります。
-
ポイント: 元社員との良好な関係維持が前提となるため、退職時の円満な関係構築と、その後の継続的なコミュニケーションが重要です。現職社員のエンゲージメント向上にも寄与する可能性があります。
【課題・目的別】自社に最適な採用のやり方の選び方
採用活動を成功させるには、自社の課題や目的に合った手法を選ぶことが重要です。ここでは、よくある4つのケース別に、推奨される採用手法とその理由を解説します。
ケース1:採用コストを抑えたい場合
限られた予算で効果を出すには、無料または低コストの手法を組み合わせます。
- 推奨手法: ハローワークでの求人掲載、リファラル採用制度の導入、SNS活用(X、Facebookなど)。
- ポイント: リファラル採用は紹介料を抑えられ、SNSは無料で情報発信できます。ただし、SNSは担当者のリソースと計画性が重要です。
ケース2:とにかく早く人材を確保したい場合
スピード重視なら、人材紹介会社との連携が最も効果的です。
-
推奨手法: 人材紹介会社との連携、求人広告の有料オプション活用。
-
ポイント: エージェントは迅速な人材紹介が可能で、求人広告は有料オプションで応募数を最大化できます。迅速な選考プロセスと柔軟な面接日程調整も重要です。
まとめ:自社に合った採用のやり方を見つけ、成功させよう
本記事では、採用活動の全体像から具体的な手法、実践的なステップまでを網羅的に解説しました。最も重要なのは、まず自社の課題と目的を明確にし、それに合った採用手法を選択・実行することです。
採用活動は一度きりの取り組みではなく、継続的な改善が必要なプロセスです。各ステップでの成果を測定し、次回の採用活動に活かすことで、組織の採用力を着実に向上させることができます。
中小企業の採用やり方においても、限られたリソースの中で効果的な採用を実現するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。本記事で紹介したテンプレートやチェックリストを活用し、自信を持って採用活動の第一歩を踏み出しましょう。
レジェンダ担当者のコメント
当社がご支援する中で多く寄せられるのは、「採用手法が多様化し、何から着手すべきか分からない」「日常業務と並行して新しい施策を試す余力がない」という声です。実際、ある企業では採用チャネルを増やしたものの、運用負荷が高まり承諾率が低下。当社がデータで現状を可視化し、面接官トレーニングを導入した結果、評価のブレが減り、早期離職率が改善しました。こうした取り組みは、再募集や教育にかかるコスト削減にも直結します。採用は目先の成果を追う「点」から、長期的な資産となる「線」へ。自社に合った手法選びや体制づくりにお悩みなら、まずは現状分析から。当社が戦略的パートナーとして改善案をご提案します。
この記事の監修者
金濵 祐香子
採用支援事業部
■経歴
通信・IT・メーカー・製造・小売など、さまざまな業界のクライアントを担当し、新卒・中途採用の支援をPMとして推進。常駐・遠隔の両形態で支援を行い、リクルーター・面接官・バックオフィス統括等の役割を担いながら、選考設計から運用まで一貫して支援している。
採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る
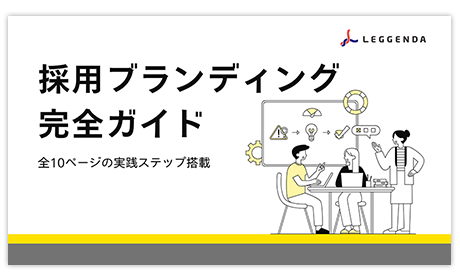 資料を受け取る
資料を受け取る
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
人事ナレッジ集トップに戻る

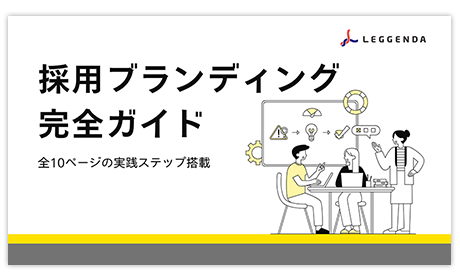 資料を受け取る
資料を受け取る

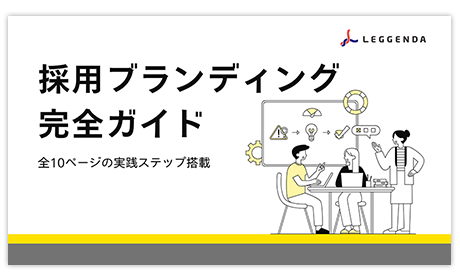 資料を受け取る
資料を受け取る





