
「なかなか良い人材が採用できない」「採用しても早期退職が多い」「採用コストがかかりすぎる」という採用の悩みを抱えていませんか?
その原因は、場当たり的な採用活動にあるかもしれません。人材獲得競争が激化する今、成功する企業が実践しているのが「採用設計」です。
採用設計とは、経営戦略に基づいて計画的・体系的に採用活動を構築するアプローチのことです。
本記事では、採用設計の基本から実践方法、成功事例まで徹底解説します。
これを読むことで、採用の質を高めながらコストを最適化し、自社の成長に貢献する人材を効率的に獲得するヒントが得られます。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る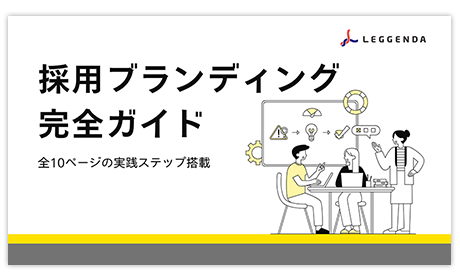 資料を受け取る
資料を受け取る
優秀な人材の確保が企業の競争力を左右する時代となりました。
採用市場の激化と人材不足が叫ばれる中、場当たり的な採用活動ではもはや成果を上げることが難しくなっています。
そこで注目されているのが「採用設計」という考え方です。
採用設計とは、単なる人材募集ではなく、経営戦略に基づいた計画的・体系的な採用の仕組みづくりを指します。
本記事では、下記採用設計の基本から実践的なポイントまで、組織の成長を支える採用設計について詳しく解説します。
採用設計とは、企業の経営戦略や事業計画に基づいて、「いつ」「どのような人材を」「どのように」採用するかを体系的に設計するプロセスです。
採用設計を導入すると、単に人材を募集して選考するだけではなく、組織の将来像を見据えた上で、必要な人材の質と量を計画的に確保できます。
採用設計の重要性が年々高まっている理由は3つあり、第一に人材獲得競争の激化です。
令和6年12月に発表された厚生労働省「雇用動向調査(令和6年上半期)」によると、前年同期と比較して入職率は9.0%、離職率は8.4%低下しています。
この結果から、多くの企業が雇用の定着施策を強化していると考えられるため、採用設計を基盤とした戦略的なアプローチが不可欠です。
第二に、採用ミスマッチの防止です。
採用のミスマッチは、採用コストの無駄遣いだけでなく、組織文化や既存社員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。
採用設計を導入すると、企業と候補者の相互理解を深め、定着率の向上や早期戦力化が期待できます。
第三に、長期的な組織成長の基盤づくりです。
「人」は企業の最も重要な資産であり、どのような人材をどのように迎え入れるかは、組織の将来を決定づける重要な要素です。
適切な採用設計を行うことで、単なる人員補充ではなく、組織の成長戦略に沿った人材の獲得が可能になります。
また、採用活動の効率化によるコスト削減や、採用ブランディングの強化にもつながります。
採用設計なしに採用活動を行うと、さまざまな問題が発生します。
一般的な問題は、「急な欠員に対する場当たり的な採用」です。
誰かが退職したから慌てて募集をかけるという対応では十分な検討時間がなく、妥協した採用になりがちです。
その結果、スキルや組織適性が不十分な人材を採用してしまい、定着率の低下や生産性の悪化を招くケースは珍しくありません。
また、採用設計がないと「採用基準のブレ」も生じます。
選考官によって評価基準が異なったり、その時々の状況で採用のハードルが上下したりすると、組織としての一貫性が失われます。
これは、採用された社員間の能力格差を生み、チームワークや公平感に悪影響を及ぼします。
「採用コストの増大」も見逃せない問題です。計画性のない採用活動は、広告費の無駄遣いや選考プロセスの非効率化を招きます。
さらに、入社後のミスマッチによる早期退職が増えると、採用からオンボーディング(人材育成の施策)までのコストが無駄になる恐れがあります。
「組織文化の希薄化」も問題です。
明確な採用設計なしに人材を受け入れ続けると、組織としての価値観や文化が曖昧になり、一体感のない職場環境につながりかねません。
特に成長フェーズの企業では、この問題が顕著に表れます。
従来の採用活動と採用設計の違いは「視点」にあります。
従来の採用活動は、「欠員を埋める」という視点から行われることが多く、目の前の人材ニーズを満たすことがおもな目的とされていました。
対して採用設計は、経営戦略や事業計画と連動した「組織づくり」の視点から採用を捉えます。
もう一つの大きな違いは「時間軸」です。
従来の採用活動は、現在の課題解決を目的としていましたが、採用設計では中長期的な組織の成長を見据えた人材獲得計画を立てます。
例えば、新規事業立ち上げの1年前から必要人材の要件定義や採用チャネルの検討を始めるといったアプローチです。
「プロセスの体系化」も重要な違いです。従来の採用活動では、募集から内定までの流れは存在していましたが、それぞれのステップが独立していることが多くありました。
一方、採用設計では、採用要件の定義から入社後のフォローアップまでを一貫したプロセスとして捉え、各ステップの連携を重視します。
最後に「データ活用」の違いも見逃せません。
採用設計では、過去の採用データや市場動向、競合分析などの客観的データを活用し、PDCAサイクルを回しながら継続的に採用プロセスを改善していきます。
従来の採用活動では、このようなデータを根拠とするアプローチは必ずしも一般的ではありませんでした。
つまり、将来への備えか、目の前の対応かという視点の違いが、採用設計と従来の採用活動が異なる点です。
採用設計の重要性を理解したところで、次は具体的にどのように進めていけばよいのでしょうか。
効果的な採用設計は、単なる思いつきではなく、綿密な計画と実行が求められます。
ここでは、成功する採用設計を実現するための5つのステップを詳しく解説します。
これらのステップを丁寧に踏むことで、自社に最適な採用の仕組みを構築することができるでしょう。
効果的な採用設計の第一歩は、自社の現状を客観的に把握し、課題を明確にすることです。
まずは、過去1〜3年の採用実績を振り返り、以下のポイントを分析しましょう。
採用計画に対する充足率はどうだったか。予定通りの人数を採用できていたか、あるいは未達成だったか。
また、採用できた人材の質は期待に沿うものだったか。さらに、採用チャネル別の応募者数や内定承諾率、入社後の定着率なども重要な指標です。
これらのデータを集計し、どの部分に課題があるのかを特定します。
次に、現在の採用プロセスを詳細に洗い出します。
募集から内定、入社までの各ステップにおいて、どのような選考基準で、誰が、どのように判断しているのか。そのプロセスは効率的に機能しているのか、あるいはボトルネックが存在するのか。この分析により、改善すべきポイントが見えてきます。
さらに、採用に関わる社内リソースの状況も確認しましょう。
人事部門のキャパシティ、採用担当者のスキルレベル、採用予算の規模など、自社の「採用力」を正確に把握することが重要です。
リソースが限られている場合は、外部サービスの活用も検討する必要があります。
これらの分析を通じて、「応募者数は多いが質が低い」「内定辞退率が高い」「入社後3ヵ月以内の離職が多い」といった具体的な課題が見えてくるでしょう。
課題の優先順位をつけ、採用設計の方向性を定めていきます。
現状の分析ができたら、次は採用要件と理想の人材像を明確にします。
このステップでは、経営戦略や事業計画を踏まえて、「どのような人材が必要か」を具体的に定義していきます。
まず、経営層や事業部門の責任者と連携し、中期経営計画や事業戦略に基づいた人材ニーズを把握します。
今後3〜5年で組織をどのように成長させたいのか、そのために必要な人材は何か、といった視点で議論を深めます。
単なる「人手不足の解消」ではなく、「組織の成長に必要な人材」という観点が重要です。
次に、職種やポジションごとに具体的な要件を定義します。
必須のスキルや経験は何か、あると望ましい資格や知識は何か、といった「ハードスキル」に加え、チームワーク力や主体性、学習意欲といった「ソフトスキル」も明確にします。
特に、自社の企業文化に適合する人材の特性は何かを検討することが重要です。
さらに、これらの要件を「ジョブディスクリプション(職務記述書)」としてまとめます。
ジョブディスクリプションには、職務内容、必要なスキル・経験、期待される成果、評価基準などを具体的に記載しましょう。
これは採用活動における「共通言語」となり、評価基準の統一に役立ちます。
また、理想の人材像を「ペルソナ」として具体化することも効果的です。
「30代前半、Web系企業でのマーケティング経験5年以上、データ分析ツールに精通、チームリーダー経験あり」といった具体的なイメージを持つことで、採用活動の方向性が明確になります。
理想の人材像が定まったら、次はその人材にリーチし、適切に評価するための採用手法と選考プロセスを設計します。
具体的には、採用チャネルの選定から選考フローの構築、評価基準の設定です。
まず、ターゲット人材にリーチするための採用チャネルを選定します。
求人媒体、人材紹介会社、ダイレクトリクルーティング、社員紹介、SNSなど、さまざまな選択肢がありますが、ステップ2で定義した人材ペルソナに合わせて最適なチャネルを選びましょう。
例えば、若手エンジニアを採用したい場合は、テック系の就職・転職イベントやIT特化型の求人サイトが効果的です。
経験豊富な管理職を探すなら人材紹介会社を活用しましょう。
次に、選考プロセスをデザインします。
一般的な流れは「書類選考→一次面接→二次面接→最終面接→内定」ですが、職種や採用難易度に応じてカスタマイズが必要です。
例えば、エンジニア職ではコーディングテストを、営業職では模擬プレゼンテーションを取り入れるなど、実務に即した評価方法を検討します。
選考のステップごとに、評価する項目と担当者、所要時間などを明確にし、効率的なプロセスを構築しましょう。
また、各選考ステップでの評価基準と評価シートも作成します。
例えば、「コミュニケーション力」を評価する場合、単に「良い・悪い」ではなく、「自分の考えを論理的に説明できるか」「質問の意図を正確に理解して回答できるか」といった具体的な観点で評価できるようにします。
これにより、選考者による評価のブレを最小限に抑えることができます。
さらに、応募者体験の設計も忘れてはなりません。応募から内定まで、応募者にどのような体験を提供するか考えましょう。
具体的には、迅速なフィードバック、丁寧な企業説明、面接官の態度など、細部にわたる配慮が採用成功率を高めます。
効果的な採用設計は、これら5つのステップを着実に実行し、継続的に改善していくことで実現します。
採用設計の基本的な流れを理解したところで、実際にどのような採用設計が成果を上げているのか、具体的な事例から学んでみましょう。
企業規模や業種によって最適な採用設計は異なりますが、成功事例には共通する要素があります。
ここでは、中小企業、採用コスト削減と質向上の両立、スタートアップの事例を通して、実践的なポイントを解説します。
中小企業の場合、大手企業のような知名度や潤沢な採用予算がないことが多いため、独自の工夫が求められます。
まずは、ある従業員80名のIT企業の事例を見てみましょう。
この企業では、採用市場での競争力を高めるため、自社の「強み」を明確にした採用設計を行いました。
具体的には、「少数精鋭のフラットな組織で裁量権が大きい」「一人ひとりの成長を全力でサポートする」という自社の特徴を押し出した採用ブランディングです。
求人票にも実際の社員の声やキャリアストーリーを掲載し、大手企業にはないアピールポイントを強調しました。
また、採用チャネルは求人サイトの他に、紹介者と入社者の双方に特典を設けた紹介制度を導入し、社員の積極的な紹介を促進しました。
さらに、地元の大学との産学連携や、業界イベントへの登壇なども採用チャネルとして活用し、自社に適した人材との接点を増やしています。
選考プロセスでは、「カルチャーフィット」を重視した独自の評価基準を設定。技術スキルだけでなく、「主体性」「学習意欲」「チームワーク」といった自社文化に適合する要素を評価する面接手法を導入しました。また、最終面接には必ず経営者が参加し、会社の展望や期待を直接伝えることで内定承諾率を高めています。
この取り組みにより、応募者数は前年比120%、内定承諾率は85%にまで向上しました。
また、入社後6ヶ月の定着率も95%と高水準を維持しています。
限られたリソースの中でも、自社の特徴を活かした採用設計により、優秀な人材の確保に成功した好例といえるでしょう。
ここでは、製造業の中堅企業の事例を紹介します。
この企業では、採用コストの大部分を占めていた求人広告費と人材紹介会社への支払いを見直すため、データ分析に基づく採用設計を実施しました。
まず、過去3年分の採用データを分析し、「どの採用チャネルから入社した社員が高いパフォーマンスを発揮し、長く定着しているか」の検証から始めます。
その結果、特定の業界専門の求人サイトと社員紹介からの採用者が、コストパフォーマンスに優れていることが判明しました。
この分析結果に基づき、業界特化型サイトと社員紹介プログラムの強化に予算を振り向けました。
また、採用担当者による直接スカウティングも強化し、受動的な募集だけでなく能動的なアプローチも取り入れています。
選考プロセスでは、従来多くの時間を要していた一次面接をWeb面接に切り替え、採用担当者の工数を削減。
同時に、最終面接前に「職場体験」を導入し、候補者と現場のミスマッチを防ぐ工夫を行いました。これにより、入社後のミスマッチによる早期退職が減少し、採用の質が向上しています。
さらに、採用管理システム(ATS)を導入し、応募者データの一元管理と選考プロセスの効率化の実現にも成功しました。
選考の各ステップでのリードタイムを短縮し、優秀な人材の流出を防いでいます。
この取り組みにより、採用コストは前年比で20%削減しながらも、入社後6ヶ月の評価は向上しました。
このように、戦略的なデータ活用と選考プロセスの最適化は、コスト削減と効果的な採用活動の両立を可能にします。
スタートアップの場合、成長スピードが速く、フェーズごとに必要な人材が変化するため、柔軟かつ先見性のある採用設計が求められます。
創業2年で従業員30名から100名に成長した、テクノロジースタートアップの事例を見てみましょう。
この企業では、創業初期・シリーズA・シリーズBという各成長フェーズに応じた採用設計を行いました。
創業初期は、少数精鋭のコアチーム構築に注力。創業メンバーのネットワークを活用し、「起業家精神」と「多様なスキル」を持つジェネラリスト人材を中心に採用しました。
選考では、創業者自身が全候補者と面談し、ビジョンへの共感度を重視する採用を実施しています。
シリーズA後の拡大期には、組織の基盤となる「ミドルマネジメント層」の採用に注力するため、エグゼクティブ層に強みを持つ転職エージェントと提携し、業界内の優秀な人材へのアプローチを強化しました。
同時に、組織文化の醸成と維持を重視し、「カルチャーフィット」を評価する独自の選考プロセスを導入しています。
シリーズB後の急成長期には、各部門ごとに必要な専門人材の大量採用に移行。採用チームを強化し、採用管理システムを導入することで、効率的な大量採用体制を構築しました。
また、入社後の育成プログラムを体系化し、組織への早期適応と生産性向上を支援しています。
結果として、短期間での事業成長を人材面から支えることに成功しています。先見性と柔軟性を備えた採用設計の好例といえるでしょう。
これまで採用設計の基本的な考え方やステップ、成功事例について見てきました。
ここでは、自社の採用設計を成功に導くための実践的なヒントを紹介します。
採用は一度作り上げて終わりではなく、継続的に改善していくものです。
以下のポイントを参考に、自社に合った採用設計を構築・改善していきましょう。
経営者に求められる役割は、まず「採用の重要性の認識と投資判断」です。
人材採用は単なるコストではなく、組織の成長のための投資であることを理解し、適切なリソース配分を行うことが必要です。
また、将来の事業展開や組織変革を見据えた採用の方向性を人事部門に明確に伝えることで、戦略的な採用設計が可能になります。
さらに、経営者自身が「採用プロセスへの関与」を通じて、自社が大切にする価値観や目指す方向性を候補者に直接伝えることも効果的です。
特に経営幹部や重要ポジションの採用では、経営者の関与が採用成功率を高める要因となります。
一方、人事担当者には「採用設計の専門家」としての役割が求められます。
労働市場の動向や採用手法のトレンドを把握し、自社に最適な採用設計を提案・実行することが重要です。
また、「事業部門との橋渡し役」として、各部門の採用ニーズを正確に把握し、採用要件に落とし込む役割も担います。
さらに、応募者数、内定承諾率、定着率などの採用データを継続的に分析し、採用設計の改善点を見つけ出すことが求められます。
これらの分析結果を経営層や事業部門にフィードバックし、より効果的な採用設計への改善を主導することが人事担当者の価値を高めます。
このように、経営者と人事担当者が密に連携し、それぞれの役割を果たすことで、戦略的かつ効果的な採用設計が実現します。
採用設計の精度を高め、継続的に改善していくためには、データの活用が欠かせません。
まず重要なのは「採用KPIの設定」です。
応募者数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率、入社後の定着率など、採用プロセスの各ステップにおける指標を設定し、定期的に測定します。
これらの指標を時系列で比較することで、採用活動の傾向や課題が見えてきます。
次に採用チャネルを分析しましょう。
求人サイト、人材紹介会社、社員紹介など、各採用チャネルからの応募者数、採用数、採用コスト、入社後のパフォーマンスを比較分析することで、自社に最も効果的なチャネルを特定できます。
限られた採用予算を効果の高いチャネルに集中投下することで、コストパフォーマンスが向上します。
「選考プロセスの効率分析」も重要なポイントです。
各選考ステップにおける所要時間や通過率、候補者のドロップアウト理由などを分析し、ボトルネックを特定します。
例えば、一次面接から二次面接までの期間が長すぎることで優秀な候補者が他社に流れているならば、そのプロセスの短縮が課題となります。
入社後のパフォーマンスデータと採用データの関連分析も有効です。
「どのような特性や経験を持つ人材が入社後に高いパフォーマンスを発揮しているか」を分析することで、採用要件の精緻化が可能になります。
例えば、特定の業界経験よりも学習意欲の高さが業績に相関している場合、採用基準の重点を変更するといった判断ができます。
これらのデータを活用するには、採用管理システム(ATS)などのツール導入も検討すべきでしょう。
応募者情報の一元管理や選考プロセスの可視化、各種分析レポートの自動生成など、データ活用の基盤となります。
データ活用の最終目標は「採用設計のPDCAサイクル確立」です。
データ分析に基づいて採用設計を改善し、その効果を測定して次の改善につなげるサイクルを続けることで、自社に最適な採用の仕組みが構築されていきます。
人事部門のリソースが限られていると、注力すべき業務に集中できず、生産性が低下する恐れがあります。
そこで有効なのが、外部リソースの戦略的な活用です。
まず検討したいのは「採用代行サービス」の活用です。
採用代行サービスは、求人原稿の作成・掲載から応募者対応、書類選考、一次面接までを代行するサービスで、人事担当者の工数削減に大きく貢献します。
特に応募が多数見込まれる職種や、定期的に発生する採用では、採用代行の活用で内部リソースを他の重要業務に振り向けることができます。
次に「採用コンサルティング」の活用も効果的です。
採用市場に精通したコンサルタントの知見を借りることで、自社の採用設計の課題発見や改善策の立案が迅速に進みます。
特に採用設計の経験が少ない企業では、一から構築するよりも、プロの知見を活用する方が遠回りせずに成果を上げられることが多いでしょう。
「採用管理システム(ATS)」の導入も、採用業務の効率化に貢献します。
応募者情報の一元管理や選考プロセスの自動化、データ分析機能などにより、人事担当者の作業負荷を軽減しながら、採用の質向上が期待できるでしょう。
中小企業やスタートアップでは「採用代行・人事アウトソーシング」の活用も一つの選択肢です。採用から入社手続き、労務管理までトータルで任せられるサービスを利用すれば、少ないリソースでも質の高い採用活動が可能になります。
自社の強みを活かした採用ブランディングや最終選考に注力し、それ以外のプロセスは外部に委託するといった役割分担が効果的です。
なお、外部リソースを活用する際の重要なポイントは、「何を自社で行い、何を外部に委託するか」の線引きです。
例えば「最終的な採用判断」や「自社文化の伝達」は内製し、定型的な業務や専門性が求められる業務は外部に委託するという考え方が一般的です。
この線引きを明確にした上で外部パートナーと連携することで、効率的かつ効果的な採用設計が実現します。
多様な外部リソースを活用しながら、限られた社内の人手や時間を効率的に使い、質の高い採用設計につなげましょう。
採用設計に関するよくある質問をまとめました。
A: まずは自社の経営計画から必要な人材を洗い出し、優先順位をつけましょう。
採用要件と理想の人材像を明確にし、自社の強みを活かした採用メッセージを考えます。
小規模企業の場合は、大企業のような豪華な待遇ではなく、「裁量権の大きさ」や「成長機会の豊富さ」などの強みを活かした採用ブランディングが効果的です。
採用管理システムの導入や一部業務の外部委託も検討すると、1人でも効率的に採用設計を進められます。
全てを一度に行う必要はなく、重要な職種から段階的に取り組みましょう。
A: いくつかの視点から改善策を検討する必要があります。
まず、採用ターゲットと採用チャネルのマッチングを見直しましょう。ターゲットとする人材がよく利用する媒体に情報を届けられているか確認します。
次に、求人内容の魅力度をチェックします。給与・待遇面だけでなく、仕事の魅力や成長機会、企業文化などを具体的に伝えられているでしょうか。
競合他社の求人と比較して、差別化ポイントが明確になっているか確認することも有効です。
また、応募の際に求めるスキルが高すぎたり、プロセスが複雑すぎたりしていないか、応募しやすさを再確認してみましょう。
さらに、社員による口コミや評判も影響するため、社内の働きやすさや従業員満足度を高めることも、間接的に応募増加につながります。
これらの改善を図ることで応募数の増加が期待できます。
A: 大きく分けて「採用プロセスに関するデータ」と「入社後のパフォーマンスデータ」の2種類があります。
採用プロセスのデータとは、応募者数、採用チャネル別の応募数と採用数、各選考ステップの通過率、選考にかかる日数、内定承諾率などです。
採用プロセスのデータを活用すると、採用チャネルや職種、時期などの軸で分析できるため、採用活動の効率性や有効性が見えてきます。
入社後のデータとは、定着率(3ヶ月・6ヶ月・1年など)、業績評価、キャリア進捗を指します。
採用のプロセスデータと組み合わせることで、「どのような特性を持つ人材が活躍しているか」という洞察が得られます。
また、定性的なデータも重要なため、入社理由や退職理由のヒアリング結果、候補者からのフィードバックなども参考にしましょう。
データ分析を継続的に行いトレンドや変化を捉えることで、より効果的な採用設計の改善につなげられます。
本記事では、戦略的な「採用設計」について詳しく解説してきました。
採用設計とは、単なる人材募集ではなく、経営戦略に基づいた計画的・体系的な採用の仕組みづくりを指します。
場当たり的な採用活動とは異なり、中長期的な組織成長を見据えた戦略的なアプローチが特徴です。
採用設計の重要性は、人材獲得競争の激化、採用ミスマッチの防止、長期的な組織成長の基盤づくりという3つの観点から高まっています。
採用設計なしに採用活動を行うと、場当たり的な採用による人材のミスマッチ、採用基準のブレ、採用コストの増大、組織文化の希薄化といった問題が生じるリスクがあります。
効果的な採用設計を実施するためには、5つのステップが重要です。
まず、自社の現状と課題を分析し、次に採用要件と理想の人材像を明確化します。
そして、採用手法と選考プロセスを設計し、実行後はデータに基づく振り返りと改善を行います。
このサイクルを継続的に回すことで、自社に最適な採用の仕組みを構築することができます。
成功事例からは、企業の規模や状況に応じた採用設計の工夫が見えてきました。
中小企業では自社の強みを活かした採用ブランディングと独自の評価基準、採用コスト削減と質向上の両立ではデータ分析に基づく選択と集中、スタートアップでは成長フェーズに合わせた先読みの採用戦略が効果を発揮しています。
採用設計を成功させるためには、経営者と人事担当者の適切な役割分担と連携が欠かせません。
経営者は採用の重要性を認識し投資判断を行い、人事担当者は専門的知見を活かして最適な採用設計を提案・実行します。
また、客観的なデータの活用によって採用設計の精度を高め、継続的に改善していくことも重要です。
リソースが限られている企業では、採用代行サービスや人事アウトソーシングなどの外部リソースを戦略的に活用することで、効率的かつ効果的な採用設計が可能になります。
採用は「人」という企業の最も重要な資産を獲得するプロセスであり、その成否は組織の将来を大きく左右します。
採用市場の変化や自社の成長に合わせて採用設計を柔軟に進化させながら、計画的かつ戦略的な人材獲得を実現しましょう。
一度作り上げて終わりではなく、定期的に見直し、改善を重ねることが採用成功の鍵となります。
自社に最適な採用設計を構築するには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢です。
採用代行や人事コンサルティングなどの外部サービスを活用しながら、自社の強みを活かした独自の採用設計を確立していきましょう。
皆さんの組織が、理想の人材を獲得し、持続的な成長を実現することを願っています。
レジェンダ担当者のコメント
採用設計は、企業の成功に不可欠な要素です。30年近く、採用活動の支援を行ってきた弊社から言えることは、場当たり的な採用活動では優秀な人材を確保することは難しいということです。急な欠員対応や一貫性の欠如、コストの無駄遣い、組織文化の希薄化を招きます。採用設計を導入することで、経営戦略に基づいた計画的な採用が可能となり、採用ミスマッチを防ぎ、定着率を向上させることができます。
成功する企業は、採用設計を通じてコスト削減と質向上を両立させ、長期的な組織成長を支える人材を効率的に獲得しています。具体的な事例を通じて、採用設計の重要性と実践方法を学びましょう。
この記事の監修者
中津川
セールス&マーケティング部 統括リーダー
■経歴
レジェンダ・コーポレーションに入社後、外資IT大手・メーカー等の新卒・中途の採用アウトソーシング、コンサルティングを担当。その後、広報、セールスを経て、現在はマーケティングに従事。インナーブランディング・Webマーケティング企画実行を担当している。

採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る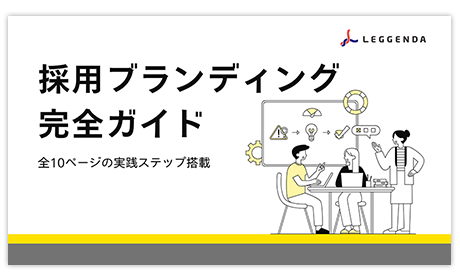 資料を受け取る
資料を受け取る
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
関連記事

採用コラム2024.09.06おすすめ採用代行(RPO)会社31社を徹底比較|導入すべきケースや選定ポイントも解説

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説
人気記事