
「応募者が集まらない…」
「求める人材と出会えない…」
新卒採用の母集団形成で、こんなお悩みはありませんか?
その悩み、実は多くの企業に共通する課題です。
本記事では、母集団形成の基本から、失敗しないためのヒント、明日から使える具体的な手法や成功事例までを分かりやすく解説します。
自社にぴったりの戦略を見つけ、理想の採用を実現しましょう。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る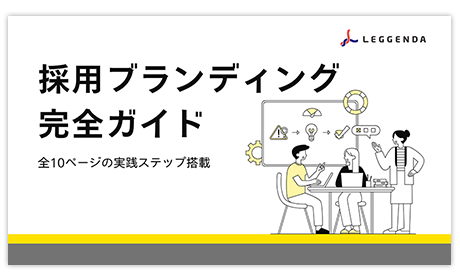 資料を受け取る
資料を受け取る
新卒採用における「母集団形成」とは、自社に興味を持ってくれる学生の集団を作ることです。
ただ数を集めるのではなく、自社にマッチしそうな学生と効率的に出会うための、戦略的な活動を指します。
どんなに良い選考を用意しても、肝心の「自社に合う学生」が応募してくれなければ、採用は成功しません。
質の高い母集団は、採用活動全体の効率を上げ、コスト削減にもつながる、まさに成功の土台なのです。
しかし、多くの企業が「応募者が集まらない」「求める人材とミスマッチが起きる」といった課題を抱えています。
母集団形成は、多くの企業にとって共通の課題となっています。
主な課題としては、「応募者数の不足」「求める人材とのミスマッチ」「採用コストの増大」が挙げられます。
特に中小企業では、知名度不足から大手企業と比較して学生の注目を集めることが困難な状況が続いています。
これらの課題を解決するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
母集団形成でつまずく企業には、いくつかの共通点があります。
自社の採用活動を振り返りながら、よくある失敗パターンを見ていきましょう。
今の学生は、ナビサイトだけでなくSNSや動画など、様々なツールで情報収集をしています。
従来のやり方だけでは、学生との十分な接点を持つのは難しいでしょう。
学生がいる場所に、こちらからアプローチすることが重要です。
「流行っているから」という理由で採用手法を選ぶのは危険です。
「多くの学生に会いたいのか」「特定のスキルを持つ学生に絞りたいのか」など、目的やターゲットを明確にしないと、時間もコストも無駄になってしまいます。
企業が伝えたいことと、学生が知りたいことにはギャップがあります。
学生が本当に求めているのは、会社の歴史や業績よりも「入社後どんな成長ができるか」「職場の雰囲気はどうか」といったリアルな情報。
学生の心に響くメッセージを届けられているか、見直してみましょう。
効果的な母集団形成を実現するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
以下の7つのステップに沿って進めることで、担当者を選ばず一定の成果を出せる、再現性の高い採用活動を構築できるでしょう。
まずは「なぜ新卒採用をするのか」をはっきりさせましょう。
単なる欠員補充なのか、将来のリーダー候補を探すのか。目的が明確になれば、採用活動全体に一貫性が生まれます。
「優秀な学生」では漠然としすぎています。
スキルや価値観、志向性など、具体的な人物像である「ペルソナ」を設定することで、どんな人にアプローチすべきかがクリアになります。
最終的な採用人数から逆算し、必要な母集団の規模を決めましょう。
過去のデータから歩留まり率(選考の通過率)を考え、エントリー数などの具体的な目標を立てることが大切です。
採用活動が早期化・長期化する今、学生がいつ動き出すのかを知ることが重要です。
ターゲット学生の行動を把握し、ベストなタイミングでアプローチできるよう年間計画を立てましょう。
設定したペルソナは、どこで情報を集めているでしょうか?
一つの手法に頼らず、イベントやSNS、研究室訪問など、複数の手法を組み合わせて学生との接点を増やしましょう。
自社の魅力を、学生の心に響く言葉で伝えましょう。
先輩社員の体験談やリアルな職場の様子など、学生が「ここで働く自分」をイメージできるような情報発信が効果的です。
各採用手法のコストを把握し、予算を計画的に使いましょう。
ただコストを削るのではなく、採用単価(CPA)を意識して、費用対効果の高い活動を目指すことが成功のカギです。
新卒採用の母集団形成に有効な主要な手法を分類し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、費用目安、適用場面を解説します。
自社の状況に最適な手法選びの参考にしてください。
時間や場所の制約を受けずに多くの学生にアプローチできるオンライン手法は、効率的に母集団の「数」を確保する際に特に有効です。
近年の採用活動の主流であり、その重要性はさらに高まっています。
リクナビやマイナビなどの大手サイトに企業情報を掲載し、学生からの応募を募る手法です。
企業が学生のプロフィールを検索し、直接スカウトメッセージを送る手法です。
人材紹介会社が企業の求める人材像に合った学生を紹介するサービスです。
XやInstagramなどのSNSを活用し、企業の日常や魅力を発信して学生にアプローチする手法です。
自社で採用専用サイトやブログを運営し、企業の魅力を発信して学生を集める手法です。
オンライン上で企業説明会やセミナーを開催し、学生に情報を提供する手法です。
YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームを活用し、企業の魅力を視覚的に伝える手法です。
学生と直接顔を合わせることで、企業の魅力や社風をリアルに伝え、強固な関係性を築けるオフライン手法です。
母集団の「質」を高め、入社意欲を醸成する際に効果を発揮します。
複数の企業が一つの会場に集まり、学生に対して企業説明を行うイベントです。
大学内で企業説明会を開催したり、キャリアセンターを通じて学生にアプローチしたりする手法です。
学生が実際に企業で就業体験を行うプログラムです。
企業と学生が少人数でじっくり話し合える形式のイベントです。
既存社員や内定者が、自身の知人である学生を企業に紹介する採用手法です。
既存の採用手法にとどまらず、外部の専門性を活用したり、ユニークな体験を提供したりすることで、他社との差別化を図り、特定のターゲットに強くアピールする際に有効なアプローチです。
採用プロセスの一部または全部を外部の専門会社に委託する手法です。
採用プロセスにゲームの要素を取り入れ、学生の興味を引きながら能力や適性を評価する手法です。
従来の手法だけでは競合他社との差別化は困難です。
現在、最新のテクノロジーやアプローチを活用した母集団形成が注目されています。
これらの手法を取り入れて、一歩先の母集団形成を目指しましょう。
AIによる書類選考や、チャットボットによる学生対応の自動化が進んでいます。
こうした技術を使えば、採用担当者は「学生と向き合う」といった、より重要な業務に集中できます。
「なんとなく」の経験に頼るのではなく、データを分析して戦略を改善する「採用マーケティング」の考え方が重要です。
どの手法が効果的だったか、どんな学生からの応募が多いかを分析し、次の戦略に活かしましょう。
母集団形成は「やりっぱなし」では意味がありません。
活動の成果をきちんと測定し、改善を続けることで、採用力は着実にアップします。
PDCAサイクルを回し続けることが成功の鍵です。
応募数だけでなく、「有効応募数」や「内定承諾率」など、採用の「質」も測れる指標を設定しましょう。
また、どの採用手法が最も費用対効果が高いかを分析することも大切です。
定期的に「良かった点(Keep)」「問題点(Problem)」「次に試すこと(Try)」をチームで話し合う場を設けましょう。
この小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。
理論だけでなく、実際の取り組み例を学ぶことで、より具体的で実践的な母集団形成のヒントを得ることができます。
以下は一般的な成功パターンをまとめたものです。
知名度で大手にかないづらい中小企業こそ、ダイレクトリクルーティングが有効です。
ターゲット学生一人ひとりに丁寧なスカウトを送ることで、大手ナビサイトでは埋もれがちな自社の魅力を直接伝えられます。
効果的なアプローチ方法:
専門スキルを持つ学生には、技術力そのものが魅力になります。
現役エンジニアが技術ブログを書いたり、SNSで学生の質問に答えたりすることで、企業のファンを増やせます。
具体的な施策例:
物理的な距離がハンデになる地方企業は、オンラインの活用が鍵です。
オンラインインターンシップやVRでの職場見学などを導入すれば、全国の優秀な学生にアプローチできます。
効果的な取り組み:
採用担当者から特によく寄せられる母集団形成に関する疑問について、実践的な観点から回答します。
これらのQ&Aを参考に、自社の採用活動をより効果的に進めてください。
A1. 必ずしもそうとは限りません。重要なのは「数」と「質」のバランスです。
多すぎる母集団は、一人ひとりへの対応が雑になり、かえって学生の満足度を下げてしまうことも。採用担当者の負担が増えすぎるのも問題です。
自社にマッチした「質の高い学生」を「適切な人数」集めることを目指しましょう。
A2. まずはコストをかけずに始められることから着手することをおすすめします。
例えば、SNSでの情報発信、大学キャリアセンターとの連携、社員の紹介(リファラル採用)などは、比較的低コストで実施できます。
何より、学生の心に響く自社の魅力は何かを考え、メッセージを磨くことが大切です。
A3. 内定辞退の多くは、入社後のイメージと現実のギャップが原因です。
母集団形成の段階から、インターンシップや社員との交流会などを通じて、仕事の良い面だけでなく、大変な面も正直に伝えることが重要です。
リアルな情報を伝えることで、納得感の高い学生が集まり、結果的に内定辞退の防止につながります。
新卒採用の成功は、応募者の「数」だけでは決まりません。自社にマッチした人材と出会うための「土台」となる、戦略的な母集団形成こそが成功の鍵を握っています。
本記事では、そのための設計図として「7つのステップ」をご紹介しました。目的を定め(Why)、理想の学生像を描き(Who)、データに基づいて計画を立てる。そして、数ある手法の中から自社に合ったものを組み合わせ、PDCAサイクルを回して改善し続けることが重要です。
忘れてはならないのは、「学生目線」でリアルな魅力を伝えること、そして感覚だけに頼らず「データ」を分析して次の一手を考えること。この2つの視点が、採用活動の精度を格段に高めてくれるでしょう。
採用環境が厳しさを増す今だからこそ、戦略的な母集団形成で他社との差をつけ、未来を共に創る理想の人材との出会いを実現していきましょう。
レジェンダ担当者のコメント
新卒採用の母集団形成は「人集め」から「戦略的人材獲得」へ進化しています。採用活動の早期化・長期化が進む中、母集団形成は「点」ではなく「線」で考える必要があります。特にZ世代の学生は情報収集手段が多様化している一方、企業の「リアルな姿」を求める傾向が強まっているため、デジタル化とリアルな接点のバランスが重要です。今後の採用活動には、AIやデータ分析を活用した効率化と、人間らしい関係構築の両立が求められると考えます。
持続可能な採用体制の構築に向けて動きたいとお考えの方は、お問い合わせからご相談ください。
この記事の監修者
金濵 祐香子
採用支援事業部
■経歴
通信・IT・メーカー・製造・小売など、さまざまな業界のクライアントを担当し、新卒・中途採用の支援をPMとして推進。常駐・遠隔の両形態で支援を行い、リクルーター・面接官・バックオフィス統括等の役割を担いながら、選考設計から運用まで一貫して支援している。

採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る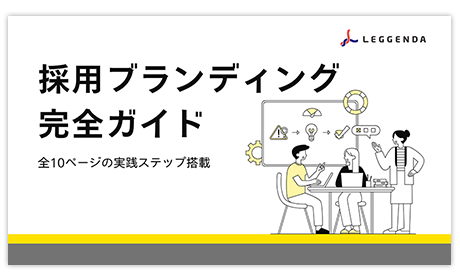 資料を受け取る
資料を受け取る
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
関連記事
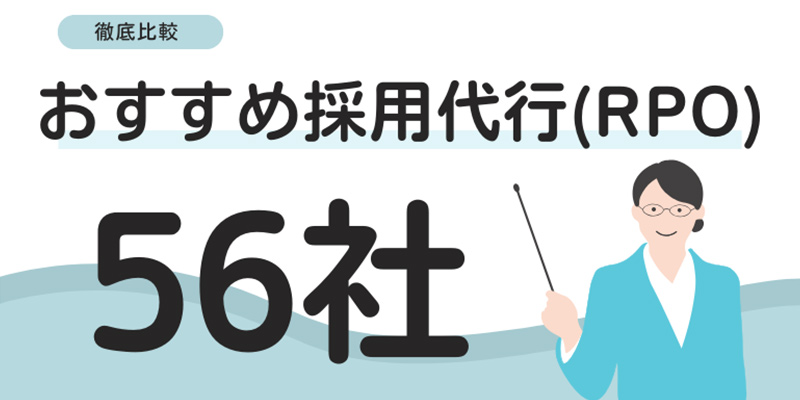
採用コラム2024.09.06【2025年最新版】採用代行(RPO)おすすめ56選!料金・サービス内容を徹底比較

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説
人気記事