
採用活動において、AIの導入が加速しています。初期スクリーニングを担う「AI面接」と、人間同士の面接にAIを同席させて候補者を評価する「面接AI」。両者は似て非なる物であり、その活用法は大きく異なります。
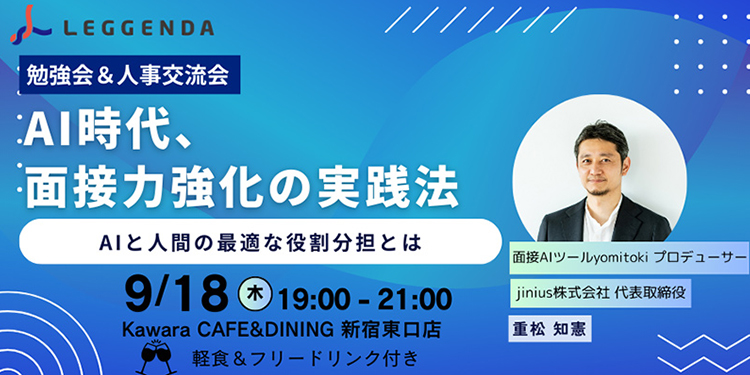
第2回を迎えた「新宿人事交流会」では、企業が直面する採用の課題と、AIがもたらす解決の可能性について具体的な事例が語られました。「人間による採用の判断が6割誤っている」という調査結果を前に、採用担当はどのようにAIを活用し、この現実を乗り越えていくべきなのか。当日の交流会から、そのヒントをお届けします。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!

まず整理しておきたいのは、「AI面接」と「面接AI」の違いである。
「AI面接」とは、アバター面接官が候補者と対話し、その会話内容を解析して初期スクリーニングを行う仕組みである。大量の応募をさばく必要がある大企業を中心に導入が進んでおり、書類選考の代替手段として工数削減に寄与している。一方、「面接AI」は人間の面接官が実施する面接にAIを同席させ、候補者の発言を分析・評価するものである。目的は単なる効率化ではなく、面接における「判断の質」を高めることにある。
「AI面接」は面接中に母集団形成の初期段階で力を発揮するのに対し、「面接AI」で同席したAIは、面接後の評価や候補者フォローといった中後段の工程で活用される。
このように役割は異なるが、共通しているのは「人間の限界を補う」という点だ。従来の採用活動では、書類選考や面接官の直感に依存する部分が大きかった。しかし、AIはそこにデータ分析を導入し、誤りを減らす役割を担っているのである。
セミナーで最も印象的だったのは、「人の評価の6割は誤っている」という調査結果だった。登壇者自身も「これまでの自分の判断の多くは間違っていたと痛感した」と述べている。では、なぜ人間は間違うのか。具体的な事例を3つ挙げて、解説した。
まずは、「採用基準と関係ない要素で判断」。人間は、自分と共通項を持つ人物を好意的に思ってしまう。バイアスによって、無意識的に評価をゆがめてしまっているのだ。これは人間の思考に組み込まれてしまっているもので、俗に言うステレオタイプ的な考え方になっている。意識的に抑えることはできるが、採用のシーンでは知らず知らずのうちに客観性を失い、適切ではない判断につながることもあるのだ。
次に、「採用基準の不備」。会社にとって大事な採用基準だが、その基準が大まかなものになっていることがある。例えば、多くの企業で、コミュニケーション力や協調性、論理的思考、主体性といった一般的に求められる能力を持つ人材を採用しようとする。さまざまな企業がある中で同じ採用基準はないはずなのに、見ている観点が同じということは、何かがズレている可能性がある。これらの凡庸な採用基準では、凡庸な人材になってしまう。各企業が本当に欲している人材を発掘するためには、より独自の評価ポイントを持つ必要がある。
最後に、「具体的なエピソードがない」ということだ。例えば、候補者が自身の主体性をアピールする際、何かしらの気づきを得たエピソードを語ることはできる。しかし、そのエピソードだけでは、実際に主体性を発揮できるかどうか分からない場合がある。その気づきが本当に行動へと結びつくのかが見極められず、判断できない状態が生じてしまうのだ。
これらの要因が積み重なり、入社後の活躍を見誤る「ギャンブル採用」が発生する。結果として新卒・中途を問わず約3割がミスマッチで早期離職し、1人あたり180万から250万円、将来的な機会損失も含めると、その15倍もの損失を生むとも考えられる。
AIは、この誤りを補正する力を持っている。回答内容の具体性や採用基準との適合度を網羅的かつ客観的に解析し、バイアスを排した評価を提供する。人間が非言語的な「雰囲気」や相性を見極め、AIがデータに基づく事実評価を担う。この役割分担こそが、精度の高い採用を可能にする鍵となるだろう。
採用活動においては、候補者が複数社を併願するのが当たり前になっている。したがって、面接後の迅速かつ丁寧なフィードバックが、候補者の面接体験を左右する。セミナーでは「辞退理由の多くは給与や条件の差にあると表向きは語られるが、実際にはフィードバックの不足が大きな要因になっている」と指摘された。

しかし、採用現場の実情は非常に厳しい。面接官からフィードバックがすぐに返ってこない、内容が薄い、あるいはバイアスがかかった情報しか得られないといったケースが多い。結果として、人事担当者は候補者に十分な情報を返せず、候補者は「大切にされていない」と感じて辞退してしまうことが度々起きている。
このような状況でも、AIが活用できる。AIは面接内容の要約、評価レポートの作成、さらには候補者に響くフォローメッセージまで自動で生成できるため、人事担当者の工数は削減され、候補者の面接体験の改善も同時に実現される。実際にAIを導入した企業の事例では、辞退率は下がり、内定承諾率が倍増したという結果も出ている。
採用は、もはや「人の勘」や「場の雰囲気」に依存できる時代ではない。AIを「スーパー客観的なパートナー」と位置づけ、判断を補強することが必要である。人間の感覚とAIの分析を組み合わせ、完ぺきではないAIを網羅的に客観的に使いこなし、候補者に適切な評価とフィードバックを返す。このような取り組みの積み重ねが、採用の成功に直結するのだ。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
関連記事

労務コラム2024.08.09今さら聞けないBPRとBPOの違い~人事BPRのメリットと進め方を徹底解説~

労務コラム2024.07.25健康経営優良法人の申請に向けた公開座談会!経営と現場、各ポジションの申請の壁と解決のヒント
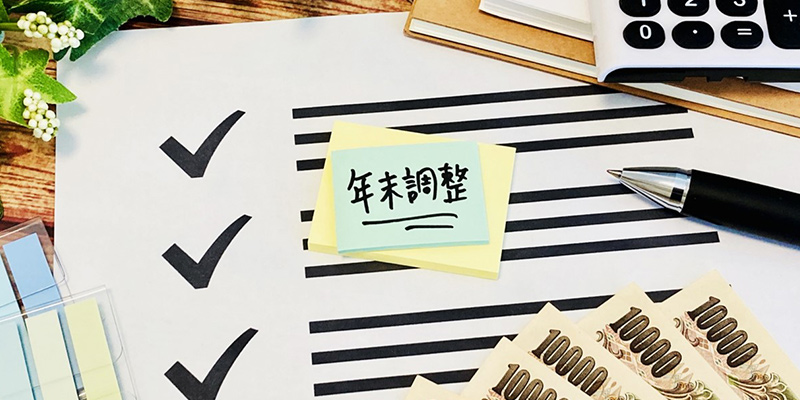
労務コラム2024.07.04年末調整のストレスから解放される方法! アウトソーシングの活用術
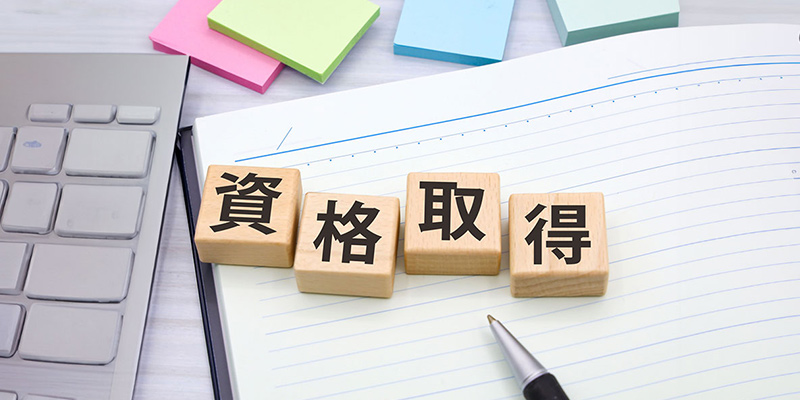
労務コラム2025.07.11【徹底解説】 健康経営優良法人2026認定制度の申請ガイドとスケジュール解説!

労務コラム2024.06.10離職防止のカギはここにあり! いますぐ企業が取り組むべき定着率向上施策

労務コラム2024.05.16定額減税(令和6年)事業者の対応とQ&A 海外赴任者はどうする?
人気記事