全国の人事パーソンへのメッセージ
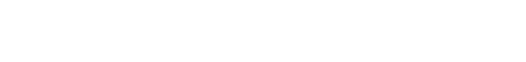
Vol036想い切りトーク

掲載日: 2025年10月31日
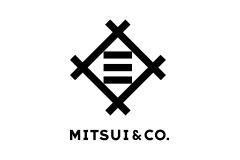
※会社名・役職等は取材当時の名称を掲載しております。
世界各地に展開する営業拠点とネットワークを活かし、金属資源からエネルギー、ICT事業まで幅広い分野で事業を展開している三井物産株式会社。同社では現在、中途採用比率が約4割に達し、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍する組織への変革を進めている。2023年4月に採用企画室長に就任した片岡弘至氏に、現場経験を活かした人材戦略とこれからの時代の人事に求められる資質についてお話を伺った。

私が三井物産に入社したのは2000年で、今年で25年目を迎えます。基本的にはずっと営業畑を歩んでおり、入社後は10年ほど紙パルプ産業、現在でいう生活資材分野の営業に従事し、その後は全く異なるエネルギー分野での事業開発を担当してきました。途中、いくつかの研修を受けさせていただく機会があり、特に入社6年目に行かせていただいたロシア研修員の経験は、その後のキャリアに大きな影響を与えました。
現在の仕事に就く前には、ロシアの現地法人で業務部長という立場で、会社のオペレーションを支えるマネジメントの経験を積みました。その後、2022年10月から現在の採用企画室に配属となり、2023年4月から室長を務めるようになりました。
はい、自分から手を挙げました。そのころは、一人前の商社パーソンとしての仕事ができるようになった時期で、今後どのように自分の価値を発揮していくのかということを真剣に考えていたんです。私は大学を卒業するまで海外に行ったことはなく、英語もそれほど得意ではありませんでした。そんな中で、どうやって自分の存在意義や価値を高めていこうかと悩んだ末に目を付けたのが英語以外の特殊言語を習得し、その地域スペシャリストになるという道でした。
当時はマーケットチャイナといって、誰もが中国に注目している時代でしたが、今から挑戦するには遅いだろうと判断したんです。そこでロシアに興味を持ち、研修に行かせてくださいと手を挙げたという経緯です。その後は、ご縁あって2020年8月から2022年10月まで現地法人の業務部長をしていましたが、2022年2月にロシアのウクライナ侵攻という未曽有の事態に直面することとなりました。
本当に想像を絶する体験でしたね。2022年2月の侵攻開始時点で、ロシア領土内には弊社関係者の日本人が約100人いたんです。オフィスに行くと大混乱で、ウクライナのキーウ事務所の近くに爆弾が落ちたという報告もありました。この未曾有の危機に対して、本社の方針は現地の判断を優先したいというものでした。業務部長の立場にあった私は、従業員とその家族の生命を守りながら、同時に事業も守る責任を負うことになったんです。
そこで、まず仕事に直接関係のない帯同家族や研修生には帰国していただき、従業員一人ひとりと話をしながら、継続できるビジネスとそれが困難なビジネスを選別していきました。現場が混乱していたこともあり、時には厳しい言葉を掛けられたこともありましたね。ですが、冷静に情報を収集し、優先順位をつけて一つひとつ判断を積み重ね、最終的には従業員を12人まで絞り込み、残った人材で結束して業務を継続しました。今、振り返ってみても自分の判断が正しかったのかは分かりませんが、結果として、当社のロシア事業は継続しておりますし、現地職員の生活も守ることができております。前例のない状況下で最後まで責任を果たしたこの経験は、当事者として考え抜き、判断することの重要性を私に教えてくれました。

求める人材像をひと言で表すと、「変化を恐れず、主体的に課題解決に取り組める人材」です。なぜこうした人材が重要かというと、総合商社のビジネスモデル自体が、時代とともに変化する社会課題に対して、常に新しい解決策を提供することで成り立っているからです。そのためには、まず好奇心を持って世の中の動きにアンテナを張り、新しい分野にも積極的に挑戦していく姿勢が必要になります。
また、どのような状況に置かれても、それを自分ごととして捉え、当事者意識を持って取り組める人材も重要です。私がロシアで直面した場面でもそうでしたが、現場では誰かの指示を待つのではなく、自ら考え、判断し、行動する姿勢が求められます。これらは、新卒・中途を問わず、すべての人材に共通して必要な要素だと考えています。
新卒採用においては、まだ社会人経験のない方々を採用するため、その方のポテンシャルを正確に見極めることが重要です。そのため、これまでの学生生活での取り組みに加えて、困難な状況での判断や行動パターンを深く掘り下げてお聞きしています。特に重視するのは、自分で考えて行動する主体性、新しいことへの好奇心、そして他者と協働できる謙虚さといった要素ですね。
また、私たちは単に一方的に選考するだけでなく、応募者の皆様とのフェアでオープンな関係を大切にしており、会社の状況や求める人物像について積極的な情報開示を行っています。選考プロセス全体を通じて、相互理解を深め、将来的な信頼関係の構築を重視したいですね。
対照的に、中途採用では即戦力としての専門性が重要となります。ただし、それと同じくらい大切なのが、これまでの経験に安住せず、新しいことに挑戦していく意欲があるかという点です。総合商社では常に変化への対応が求められるため、自己変革を続けられる方でなければ、長期的な活躍は難しいと考えています。
私たちが採用で目指しているのは、単に人材を確保することではなく、一緒に未来を作り上げていく仲間を見つけることです。弊社の英語ロゴ「MITSUI & CO.」には、三井という企業とそこで働く人々が上下の関係ではなく、対等な関係(“&”)として結ばれていることを表現しています。だからこそ、採用プロセスも一方的な選考ではなく、お互いの価値観や目標を率直に共有し合い、真の意味での相互理解を深めることを大切にしているんです。現在では、中途採用者の比率が約4割にまで増加しています。
多彩な経験を持つ人材が組織に新たな価値をもたらしてくれていて、社内もそれに適応しようとしている状況ですね。もともと弊社は自由闊達な社風で、立場にとらわれずに付加価値貢献が評価される土壌があるため、中途採用の方々もなじみやすい環境だと感じています。しかし、中途採用の比率を上げるということは、これまでの文化と変わる部分も出てきますので、既存の社員も変化していく必要があると思っています。
そうした中では、弊社がバリューの1つとして掲げている「多様性を力に」という価値観が大きな支えとなっているんです。これまで生え抜きで歩んできた社員にとっても、この価値観があることで、新しく入られる方々の力を借りて、さらにそれを吸収しながらより良いものを作り上げていこうという意識が自然と生まれています。普段から様々な専門家やパートナー企業と連携して事業を進めていることも、こうした流れを後押ししてくれているのかもしれませんね。

何より痛感しているのは、人を見るということの難しさです。選考プロセスという限られた時間の中で、その人の能力や人間性をしっかりと把握することは、想像以上に困難な挑戦なのかもしれません。しかし同時に、そうした限界を認識しながらも、日々会社の将来を思い描きながら取り組んでいくことの重要性を学びました。完璧な人材評価は難しいとしても、その中でも最善を尽くしていく姿勢が大切なのだと思っています。選考プロセスを通じて得られる情報を最大限活用し、会社と候補者双方にとって最善の判断を下そうと努力することが、採用担当者としての責務ではないでしょうか。
自分の直感や違和感を信じるということも重要だと考えています。常に判断を求められる仕事の中で、自分の判断軸がぶれたり、自分を疑ったりすることはたくさんありました。しかし思い返してみると、自分が違和感を持った時というのは、ミスマッチが発生してしまうケースが多いんです。時には、せっかく入社した方が早期に退職してしまうこともありました。もちろん、そうした直感が常に正しいわけではありませんが、長年の経験で培った人を見る目というものは、やはり大切にすべきだと思うようになりました。今では、客観的な評価とあわせて、自分の直観も重要な判断要素として位置づけています。
一方で、「分かったつもりにならない」ということも常に心に留めておく必要があります。自分の判断は基本的にこれまでしてきた経験に基づいているため、そこには限界があることを認識しなければなりません。特に、世の中の変化が加速している現在では、過去の成功体験だけに頼った判断は危険です。自分を信じつつも謙虚であり続けるというバランスが重要だと考えています。

人事は、組織の根幹である「人」と深く関わる、極めて重要な仕事です。制度設計から採用、人材育成に至るまで、私たちの判断と行動は、多くの人々のキャリアや人生に大きな影響を与えています。確かに人を相手にする仕事は難しく、正解のない判断を迫られることも多いですが、それを乗り越えた先には、人材が輝き、組織が成長していく姿があります。
今後、私たちが直面する課題はどんどん複雑化していくことでしょう。時には失敗することもあるでしょうが、その失敗から学び、次につなげていく姿勢こそが、これからの人事パーソンに求められる資質だと考えています。人材を通じて組織を強くするという共通の目標に向かって、これからも頑張っていきましょう。

国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
サービスのご紹介
おすすめ記事
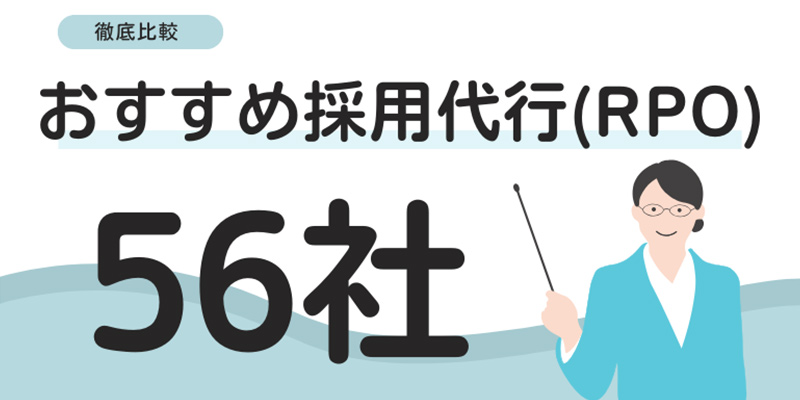
採用コラム2024.09.06【2025年最新版】採用代行(RPO)おすすめ56選!料金・サービス内容を徹底比較

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説